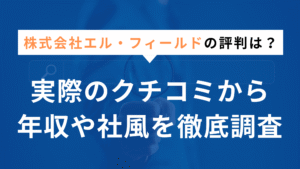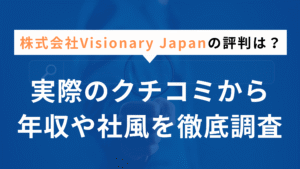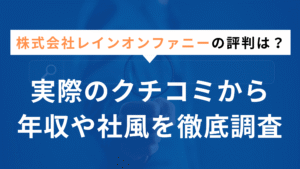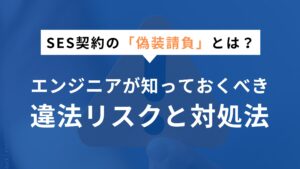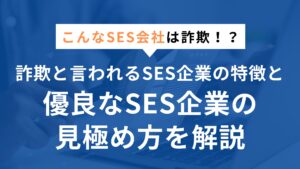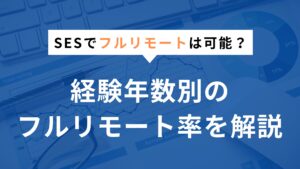SES企業がつらいと言われる理由5選!つらい・きついと感じたらどうすればいいか解説
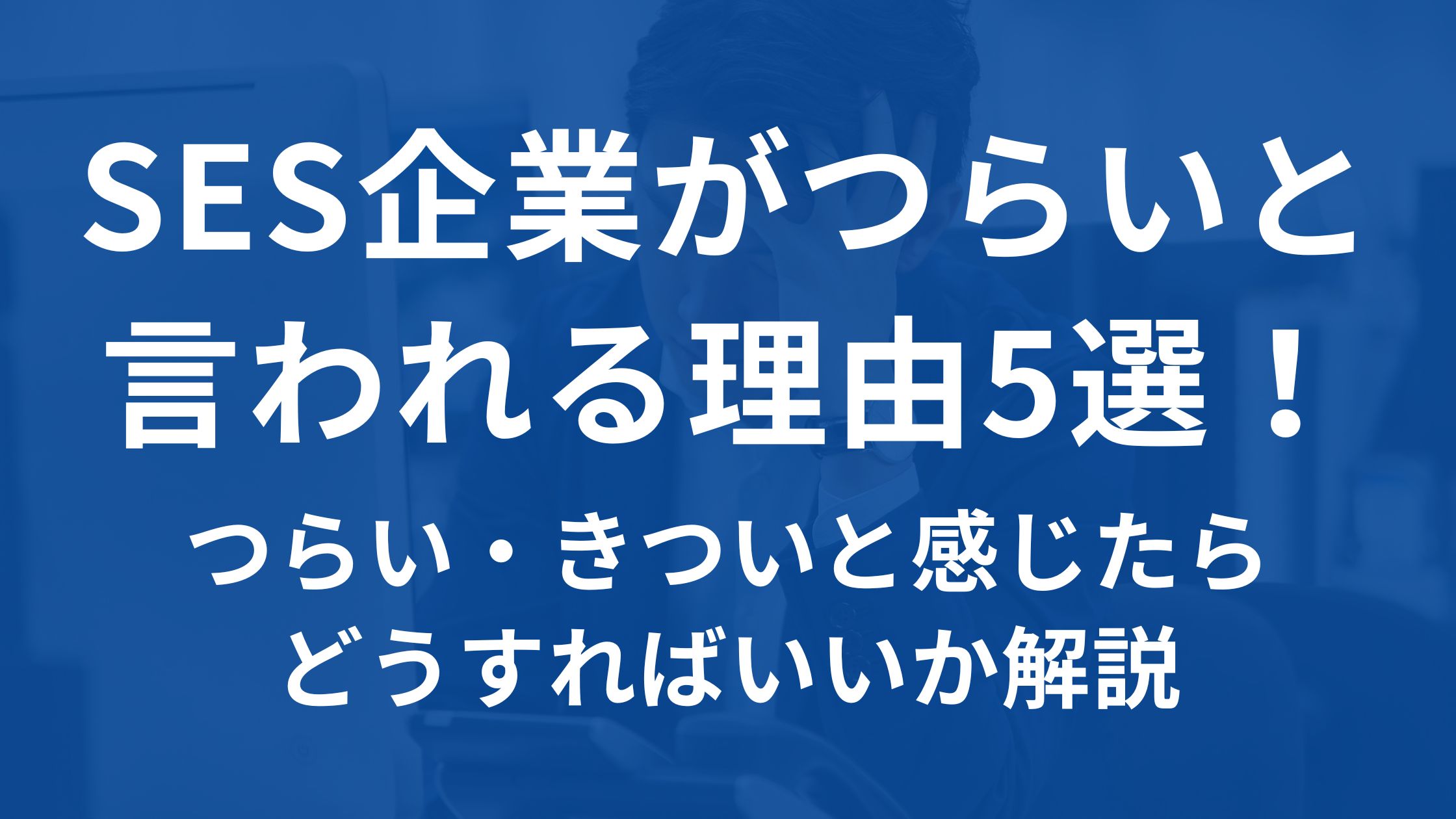
IT業界で働くエンジニアには、SES(システムエンジニアリングサービス)という働き方を選ぶ人が少なくありません。ところが「SESはつらい」「きつい」という声をSNSや口コミサイトで見かけることも多く、一部のエンジニアはその現実に苦しんでいるようです。なぜ、そのような声が絶えないのでしょうか。この記事では、SESがつらい・きついと言われる理由や対処法、さらに優良SES企業を見極めるポイントなどを詳しく解説します。
1.SESがつらい・きついと言われる理由【全5選】

SESはITエンジニアがSES企業に所属しながら、クライアント先で開発や運用保守を行う仕組みです。多様な案件を経験できるメリットがある一方、「つらい」「きつい」という声が後を絶ちません。ここでは、なぜそんなネガティブな印象が強まるのか、主な要因を整理してみましょう。
理由.1 配属先の労働環境に大きく左右される
SES最大の特徴は「就業場所がクライアント先」という点ですが、これが大きなストレス要因になることがあります。
- 長時間労働や休日出勤が当たり前の場合
もし配属されたプロジェクトが納期に追われて残業・休日出勤が常態化していたり、いわゆるブラック企業的な風土を抱えている場合、エンジニアは否応なくその環境に巻き込まれます。たとえSES企業が「残業を減らしたい」と考えていても、契約形態の都合上、実際にエンジニアを管理しているのはクライアント側なので、改善は容易ではありません。 - 休暇が取りにくい風土やシフト制の業務の場合
運用保守や監視系の案件では、夜勤シフトや休日のオンコール対応が求められるケースも多く、体力面の負担が増大します。「休みたいときに休めない」「有休が取りにくい雰囲気がある」といった問題に悩まされることも。 - 社内人事制度が現場に及びにくいことも
SES企業はエンジニアを雇用しているものの、就業先の細かいルール(勤務時間やセキュリティ規定など)には直接口を出しにくい立場です。結果として、クライアント先の環境に馴染めないエンジニアがSOSを出しても、即座に問題解決できる体制が整っていない企業も多いのが現状です。
理由.2 参画する案件を自分で選べない場合が多い
SES企業では、営業担当がクライアントから案件を受注し、そこにエンジニアを割り当てる形が一般的です。
- 「案件ガチャ」に巻き込まれるリスク
俗に「SESは案件ガチャ」とも揶揄されます。エンジニア本人が「最新のクラウド技術をやりたい」「上流工程にチャレンジしたい」と望んでいても、空いている案件が運用やテストばかりだと、希望に沿わない配属が決まってしまうことが少なくありません。 - ステップアップしにくい歯がゆさ
開発やAI・データ分析など先端領域への意欲があっても、案件選択権が自分にないために経験を積めず、スキルが停滞してしまうケースは珍しくありません。SES企業によってはある程度希望をヒアリングしてくれるところもありますが、必ずしも希望が通るとは限らない現実があります。
理由.3 多重下請けや還元率の問題
SES業界全体が抱える構造的な課題として、多重下請けや不透明なマージン率が挙げられます。
- 多重下請け構造
1次請け~2次請け~3次請け……といった形で、エンジニアが実際に配属されるまでに複数層の仲介企業が存在する場合、エンジニアに支払われる報酬が極端に削られることがあります。低賃金なのにハードな作業を強いられ、「体力的にも金銭的にもきつい」という声は後を絶ちません。 - 還元率が不透明
SES単価が月80万円でも、エンジニアに還元されるのはその半分以下という例も珍しくありません。交通費や社会保険料などがエンジニア自己負担だったり、経費名目で給料から差し引かれて実質的な還元率が大幅に下がっている企業もあります。努力に見合う報酬が得られず、「頑張っても報われない」と感じる大きな原因になっています。
理由.4 帰属意識の希薄さ・孤立感
SESエンジニアはクライアント先で仕事をするため、自社のメンバーと顔を合わせる機会が極端に少なくなることが多いです。
- 同僚と会わないまま年次が上がる
帰社日や社内イベントがあったとしても、月に1回ほどしか会わない、もしくはバラバラの案件で会えないエンジニアも少なくありません。そのため、情報交換や悩み相談の相手がおらず、精神的に孤独になりやすいのです。 - キャリアパスや評価が不透明
普段はクライアント先の上司から指示を受けているため、SES企業での公式な評価や昇進基準が曖昧になりがちです。「自分がどんな評価を受けているのか分からない」「社内に相談相手がいない」といった状況から、強い疎外感を抱くケースがあります。 - 問題が起きてもサポートが限定的
クライアント先で人間関係のトラブルや劣悪な労働環境があっても、SES企業がすぐに介入して改善できるとは限りません。営業担当や管理者が複数の案件を兼任しており、エンジニア一人ひとりの現場を把握しきれないという構造的な問題も考えられます。
理由.5 新型コロナ以降のリモートワーク対応格差
コロナ禍を経て、多くの自社開発企業やITベンチャーではリモートワークが進みましたが、SESの現場では必ずしもそうとは限りません。
- リモート非対応のクライアント先
旧来のセキュリティルールを変えたがらず、出社率100%を求める企業も多く、結果としてSESエンジニアだけが毎日客先に通わざるを得ない状況が起きています。 - 在宅勤務時の管理が不明瞭
リモート化できた場合も、SES企業の管理体制やクライアントの指示系統が整備されておらず、業務範囲やコミュニケーションルールが混乱しやすいという課題があります。「指示が曖昧なまま、ただ在宅で仕事しているだけ」「稼働時間を正確に申告できず、サービス残業が増えてしまう」などの事態も報告されています。
以上のように、SESが「つらい」「きつい」と言われる背景には、労働環境の不安定さ や 案件選択の自由度の低さ、スキルアップの難しさ、報酬や帰属意識の問題 などが絡んでいます。もちろん、SESにもメリットは存在しますが、こうした構造的な課題を理解せずに入社してしまうと、ギャップに苦しむ人が出てしまうのも事実です。次章からは、具体的な対処法や優良企業の見極め方について詳しく解説していきます。
2.SESがつらい・きついと感じた時の対処方法

もし現在、SESエンジニアとして働きながら「もう限界だ」と感じているなら、いくつかの対処法を検討してみましょう。決して一人で抱え込まず、周囲と相談しながら行動を起こすことが大切です。
- 会社(SES企業)に相談して案件変更を探る
まずは営業担当や上司に現状の問題点を伝えてみることです。残業の多さや仕事の偏りなどを具体的に話すことで、可能なら他の案件を提案してもらえるかもしれません。黙っていると「問題なく働いている」と思われてしまうため、早めに声を上げることが重要です。 - 自己学習でスキルアップを継続する
たとえ今の案件が単調でも、自宅学習やオンライン講座、資格取得などで自分の市場価値を高めるやり方があります。実務で使えない技術でも、面接やポートフォリオでアピールできるように学んでおけば、将来的なキャリアアップに大いに役立つでしょう。 - 職務経歴書(スキルシート)を見直す
「開発経験が少ない」と思っていても、運用保守やテスト工程で培ったノウハウをしっかり言語化すれば、転職市場で評価されることがあります。自分の担当業務を具体的な数字や改善内容とともにまとめ、アピール材料を作っておくと選択肢が広がるでしょう。 - プロジェクト内で役割を広げるよう交渉する
ある程度職場の雰囲気が許すなら、「もっと開発にも関わってみたい」「要件定義のミーティングに参加したい」といった意欲をクライアント先にアピールするのも手です。実際、テスト担当から開発へステップアップした例も少なくありません。 - 同業コミュニティやSNSで情報交換
SESは孤独になりがちですが、SNSや勉強会、コミュニティを通じて他のSESエンジニアがどのようにキャリア形成しているか知ると、意外な発見があります。自分だけが悩んでいるわけではないと分かれば、気持ちが楽になるかもしれません。
3.こんなSES企業はやめとけ

「つらい」「きつい」原因が会社の構造的な問題にあるなら、いくら努力しても改善が難しい場合があります。ここでは要注意な特徴を挙げてみました。
- 還元率の詳細を公表しない
SES単価やマージン率の説明がなく、「還元率80%!」などの宣伝文句だけでは実態がわかりません。面接で質問しても曖昧な回答しか得られないなら、公表している還元率と実態とで乖離している可能性が高いです。 - 待機(ベンチ)期間に給与保証がない
案件が切れて待機(ベンチ)状態になるときに、給料が出ない・激減する企業もあります。次の案件を探している間の生活が不安定になるため、エンジニアが非常に不利な立場に置かれるでしょう。 - キャリア面談や教育制度が形だけ
ホームページでは「キャリア支援に力を入れています」と謳っていても、実際にはエンジニアの希望を聞かず、ただ案件を押し付けるだけの会社もあります。社内勉強会や研修の実態がないと、スキルアップは望み薄かもしれません。こういった外からわからない制度運用の実態は、転職者向けの口コミサイトをチェックすることが有効です。
4.優良SES企業の見極め方

一方、「SES=全部ブラック」と考えるのは極端な意見と言えるでしょう。優良SES企業も確かに存在し、エンジニアを大切に扱っている会社では多様な案件や充実したサポートを受けられます。ここでは、そうしたホワイトな環境を見極めるポイントを紹介します。
- SES単価・経費の透明化
社内向けにSES単価やマージンを共有していたり、交通費や資格取得費用をどこまで会社負担とするか明確にしていたりする企業は信用度が高いです。昇給やボーナスの基準が分かりやすい点は、安心して働ける環境の特徴の1つといえます。 - キャリアサポート・研修制度の充実
定期的にキャリア面談を行い、エンジニアが「こんな案件をやりたい」「この技術を磨きたい」と希望を伝えられる仕組みがあると、モチベーションを保ちやすいです。社内勉強会や資格取得支援制度があれば、主体的に成長できます。 - 法令遵守を徹底
偽装請負や多重下請けを避けるため、契約や指揮系統をきちんと管理している会社は「エンジニアを法的にも守る」という意識が強いと判断できます。36協定や労働時間管理を厳格に行っていれば、残業代も適切に支払われるはずです。 - 社内コミュニケーションの活発さ
帰社日やイベント、チャットツールなどを通じて他のプロジェクトのエンジニアとも意見交換ができる企業は、孤立感を軽減しやすい環境です。メンター制度やリーダー面談などがあると、不安や悩みを相談しやすい雰囲気が生まれます。 - 実績・評判が良い
長く在籍する社員が多い会社や、転職サイトで「案件の選択肢が豊富」「還元率が明確」といったポジティブな意見が多い会社は注目に値します。口コミはあくまで参考程度ですが、極端にネガティブな評価が集中している企業はリスクが高いでしょう。
5.SESで働くメリット

これまで「つらい」「きつい」側面を中心に取り上げてきましたが、SESにはポジティブな要素もあります。自分のキャリアプランや性格に合えば、SESで充実した経験を積むことも十分可能です。
1.多様な案件・技術を経験できる
自社開発だと同じプロダクトを長期間扱うケースが多いですが、SESなら数か月~数年単位で新しいプロジェクトに参加できます。幅広い技術領域に触れてみたい人にとっては魅力的な働き方です。
2.未経験でも比較的採用されやすい
人手不足のIT業界で、SES企業は若手や未経験者を積極的に受け入れる傾向があります。大手自社開発企業で求められるような高度なスキルがまだない状態でも、エンジニアとしてスタートしやすいのは大きなメリットでしょう。
3.人脈を築きやすい
プロジェクトごとに新しいエンジニアやクライアントの担当者と仕事をするため、人脈が広がりやすいです。人脈が増えれば、将来的に転職やフリーランスで活かせる情報や紹介を得られる可能性も高くなります。
4.ジェネラリストとしての強み
さまざまな業種・技術領域を経験することで、「幅広い環境に柔軟に適応できる」というジェネラリスト型のスキルをアピールしやすくなります。マネジメントやコンサル志向がある人なら、知見の広さを評価される場面もあるでしょう。
6.本当につらい・きついなら転職しよう

ここまで対処法や優良企業の見極め方を紹介してきましたが、どうしても「今のSESが限界」と感じるなら、転職に踏み切るのも一つの選択です。無理して心身を消耗するより、新たな環境を探すほうが健全な場合もあります。
実際に転職を検討する際は、以下のように取り組んでいきましょう。
- 具体的な将来像を明確にする
転職先でも同じ失敗を繰り返さないためには、「自分がどんな技術を極めたいか」「どんな働き方を目指すか」をはっきりさせましょう。たとえばクラウドエンジニアを目指すならAWSやAzureの資格に注力する、自社開発志望ならWebフレームワークを重点的に勉強するなど、ゴールに向けたアクションが取りやすくなります。 - 転職エージェントを活用する
SES企業から自社開発・受託開発へ移りたい、同じSES企業でもホワイト企業に移りたいなど、さまざまなニーズに合わせた求人を見つけやすいのがエージェントの利点です。書類添削や面接対策など、プロのサポートを受けられます。 - 職務経歴書やポートフォリオの整備
保守やテストしかやってこなかったという人でも、実務で得た知識をしっかり言語化し、アピール材料に変える工夫が必要です。OSSへのコントリビュートや個人開発プロジェクトなどを並行して行っておけば、転職時の評価アップにつながります。 - ベンチ期間などのタイミングを活用
SESの案件が終了し、ベンチ状態になったときは、転職活動を進めやすいタイミングです。次の配属先に入ってからだと再び忙しくなり、行動しづらくなる場合がありますので、チャンスを逃さず情報収集を進めてみましょう。
7.まとめ
SESが「つらい」「きつい」と言われるのは、配属先の労働環境や案件選択の自由度、スキルアップの不透明さなどに起因します。もし現場での疲弊や成長の限界を感じるなら、会社や上司への相談、自己学習、優良SESへの転職など、行動を起こすことが大切です。ブラックな企業を避けて透明度が高くキャリア支援が充実した環境を選べば、SESならではの多様な経験を活かして成長する余地も十分あります。自分の将来像を明確にしながら、必要に応じて転職に踏み切る勇気を持ちましょう。