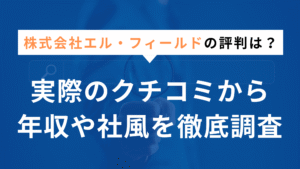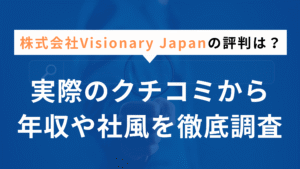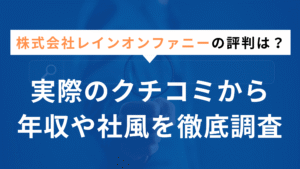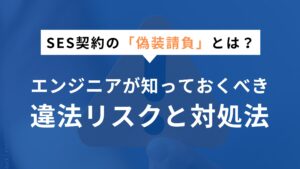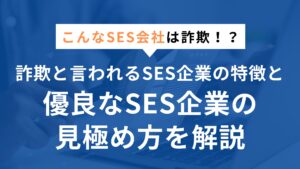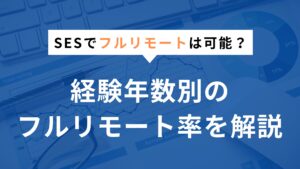SES会社勤務は正社員?SESで働くメリットや、優良SES企業の見極め方を解説
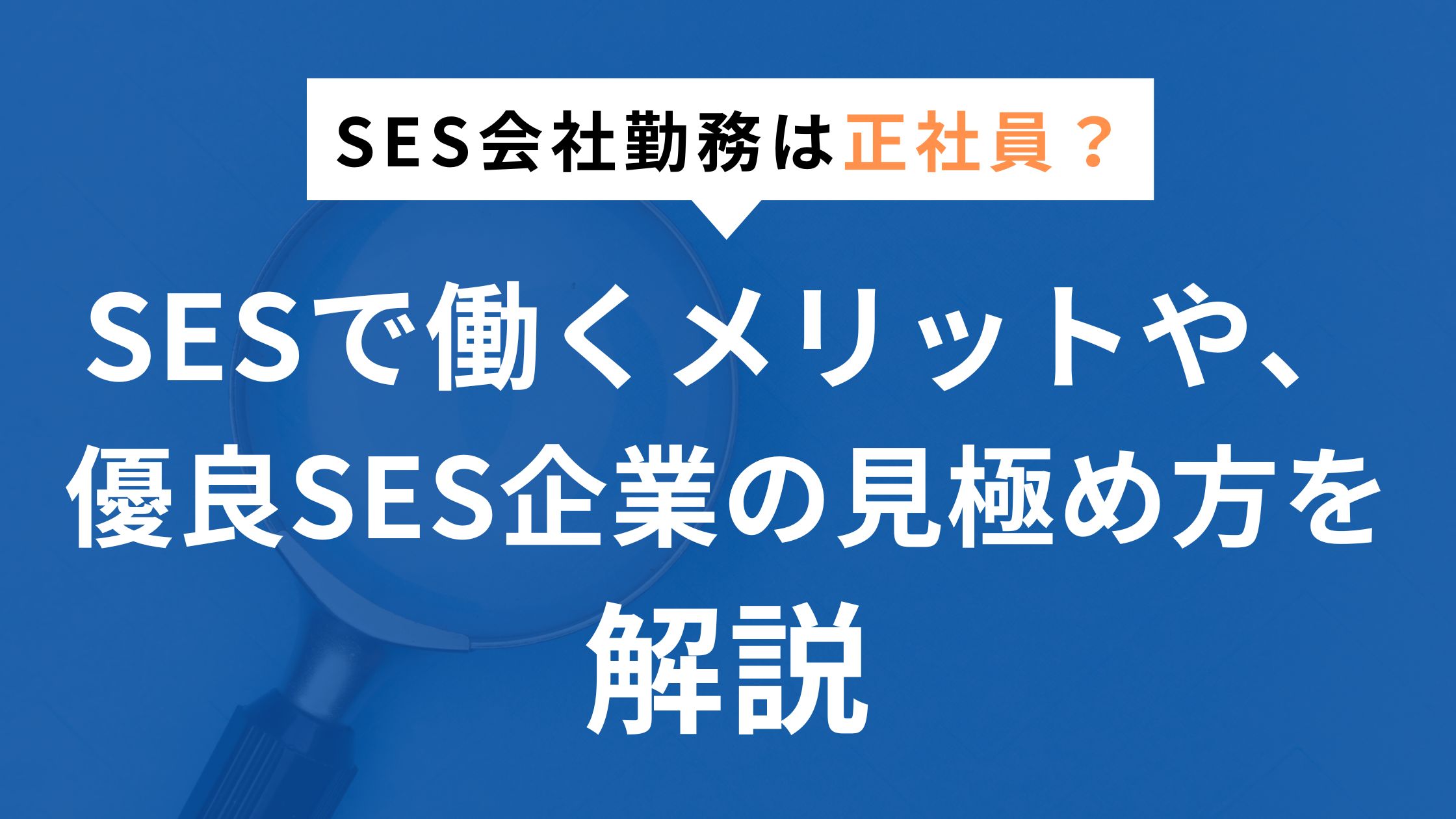
IT業界では「SES」という言葉をよく耳にしますが、具体的にどのような働き方なのかイメージしづらい人は少なくありません。たとえば、「SESは正社員なのか」「SESでキャリアアップはできるのか」「どんな企業がおすすめなのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、こうした疑問を解消するために、SESの基本的な仕組みや雇用形態、メリットやデメリット、そして優良SES企業を見極める方法を詳しく解説します。これからSESを検討する方、あるいはSES業界の現状を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.SESとは

まずは「SES(システムエンジニアリングサービス)」という言葉の意味を整理しましょう。「SES」 とは、ITエンジニアにクライアント企業へ常駐してもらい、開発や運用保守、インフラ構築などの技術支援を行うビジネスモデルのことです。派遣や請負契約と似ている部分もありますが、多くの場合は 「準委任契約」 と呼ばれる形態で行われます。
準委任契約
エンジニアが提供する「作業時間」に対して費用が発生する契約形態です。成果物の完成責任を負わない点が、請負契約との大きな違いと言えます。
正社員または契約社員として所属
SES企業に所属するエンジニアは、その企業の正社員や契約社員として雇用されます。雇用契約を結ぶ相手はクライアント企業ではなく、あくまで所属するSES企業です。
派遣との違い
派遣契約では、派遣先企業がエンジニアに直接指示を出し、法律上も「一般派遣」という枠組みに入ります。一方でSESは準委任契約が主体となるため、指示系統が派遣とはやや異なるのが特徴です。
IT業界では慢性的なエンジニア不足やプロジェクトの繁閑に応じた人材配置ニーズがあるため、SES企業への需要は高まりを見せています。それに伴い、SES企業も多くの求人を出しており、未経験や経験の浅いエンジニアにとって比較的チャレンジしやすい就業形態になっている面があります。
2.SESの働き方・仕事内容・給料

SESの需要やチャレンジのしやすさをここまでお伝えし、少し興味が湧いてきた方も多いのではないのでしょうか。
ここでは皆さんがより気になっているであろう働き方・仕事内容・給料についてお伝えします。
働き方の特徴
働き方の特徴については、SES企業においては大きく分けて3つあります。
- クライアント先に常駐する働き方が基本(例外としてリモートもあり)
SES企業に所属すると、基本的にはクライアント先に出向いてプロジェクトを進めます。SES企業のオフィスへ出社するのは月に1~2回の帰社日や面談など、最小限にとどまるケースが多いです。 - プロジェクト終了で配属先が変わる可能性がある
プロジェクト単位で契約期間が設定されていることが多く、契約が終了すれば別の現場へ移ることがあります。半年や1年でころころ変わる場合もあれば、3~5年ほど同じ現場で継続することもあります。 - クライアント企業のルールに合わせることが多い
実際の勤務時間や休憩時間、セキュリティルール、使用ツールなどはクライアント先の決まりに従うのが基本です。SES企業が直接管理できる範囲は限られるため、働きやすさは配属先次第という面があります。
仕事内容の例
SES企業においては、配属された案件によって仕事の内容が大きく変わってきます。
以下にはその一例を記載します。
- アプリケーション開発:Java、Python、C#などを用いてWebシステムや業務アプリを開発
- インフラ構築・運用:サーバー設計・構築や、AWS・Azureなどクラウド環境の設定・保守
- テスト・品質保証:システムテストの計画立案や不具合検証
- サポートデスク・ヘルプデスク:ユーザーからの問い合わせ対応やトラブルシューティング
こうしたプロジェクトはクライアント企業の要望に沿って進行するため、最先端技術に触れられる場合もあれば、古いシステムの保守運用がメインとなる場合もあります。幅広い経験が積める反面、特定の技術を深掘りしにくいという声も聞かれます。
給料の仕組みと還元率
SES企業はクライアント企業から「SES単価」を受け取り、そこからエンジニアの給与を支払っています。たとえば月〇〇万円の単価が設定され、その何割をエンジニアに還元するかが 「還元率」 と呼ばれる指標になります。
- 還元率の目安
一般的には 60~70% が平均とされますが、「還元率80%」を掲げる企業も存在します。ただし、80%と表記していても交通費・保険料などがエンジニア負担の場合もあり、実質的な手取りが必ずしも高いとは限りません。 - 給与形態
多くのSES企業では正社員として月給制を採用していますが、賞与(ボーナス)や昇給、諸手当の有無、評価基準などは会社によって大きく異なります。入社前に給与明細の仕組みや手当の詳細を確認することが大切です。
3.SES契約と請負契約の違い

SESと請負はよく混同されがちですが、契約形態が根本的に異なります。
請負契約
- 成果物に対して責任を負う契約
- 完成物の納品がゴールであり、納期や品質の責任は請負企業(ベンダー)が負う
- クライアント企業が直接エンジニアに指示を出すのはNG(偽装請負となる恐れ)
SES(準委任)契約
- 作業提供や稼働時間に対して対価が支払われる
- 成果物の完成責任は負わない
- 法律上はエンジニアを管理するのはSES企業だが、実態としてクライアントから指示を受けることも多い
SESの強みは「成果物ではなく作業工数に対して報酬が発生するため、要件変更や仕様変更があっても柔軟に対応しやすい」点にあります。しかし、完成責任を負わない という性質上、エンジニアがプロジェクト全体のマネジメントに携わる機会が少ないのも事実です。
4.SESとして働くメリット

SESとして働くと、どのような利点があるのでしょうか。ここでは代表的なメリットを挙げてみます。
1. 幅広い技術や案件を経験できる
多種多様なクライアント先で、さまざまな分野や工程に携われる可能性があります。自社内でずっと同じプロダクトを開発する場合と比べると、より多彩な技術に触れてスキルの幅を広げやすい面があります。
2. 入社ハードルが比較的低い
IT需要が高まるなか、SES企業はエンジニアを積極採用する傾向があります。未経験や経験浅めでも研修やOJTを通じて現場に送り出す体制が整っている企業も多く、エンジニアとして最初のキャリアを築きたい人には好都合です。
3. いろいろな働き方に触れられる
クライアント先ごとに開発文化や就業規則が違うため、アジャイル型やウォーターフォール型など多様なプロジェクトマネジメント手法を体験しやすいのもポイント。さまざまな現場を見て、自分に合う働き方や技術スタックを探すことができます。
5.SESとして働くデメリット

SESにはメリットがある反面、注意すべきデメリットも存在します。特に以下の点には気を配っておく必要があるでしょう。
1. 配属先や案件の選択権が弱い
SESの仕事は営業担当が受注した案件にアサインされることが多く、エンジニア自身が希望する技術・工程を選択しにくい場合があります。保守運用やテスト工程だけを延々と任され、思うようにスキルアップできないリスクも否めません。
2. クライアント先の労働環境に左右される
実際の就業場所はクライアント企業のため、SES企業の社風や制度があっても現場に反映されにくいことがあります。たとえば残業が多いプロジェクトに配属されると、SES企業の規定にかかわらず長時間労働が常態化する可能性があります。
3. 年齢を重ねた際、上流工程の経験が少ないと仕事が限られる
キャリアの年数に応じてより高いスキルが求められる傾向にあり、対応した経験がないと仕事が限られてしまう点も1つのデメリットかもしれません。具体的には上流工程(システム開発や設計の初期段階の工程で、プロジェクト全体の計画や設計を行うもの)の経験がよりキャリアを重ねると求められる傾向にあります。
6.「SES やめとけ」と言われる理由
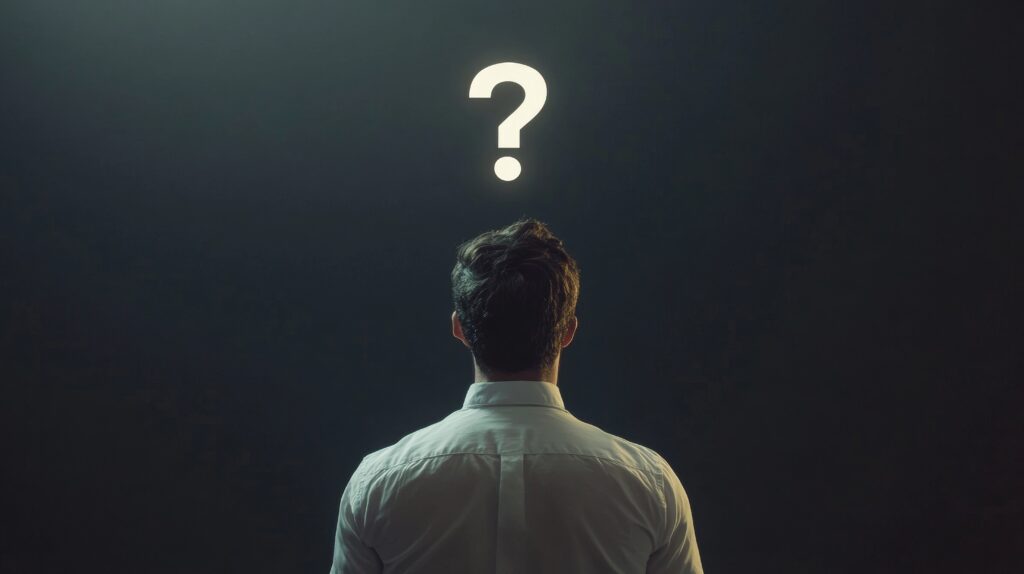
インターネットやSNS上で「SESはやめとけ」と言われることがありますが、その背景には以下のような問題が指摘されています。
- 偽装請負や多重下請けのリスク
SES企業の中には、契約形態が曖昧なままクライアント先で働かせたり、多重下請け構造による過剰なマージン抜きが横行しているケースがあります。こうしたブラック企業に当たると、エンジニアが不当な労働条件を押し付けられる恐れがあります。 - 給与・還元率の不透明性
SES単価やマージン率を社員に開示していない企業も少なくありません。自分の給与がどの程度正当なのか判断しづらく、不満や不信感につながりやすい要因となります。 - スキルアップの方向性が見えにくい
保守運用やテスト工程だけを延々と担当させられ、キャリア形成が進まずに離職する人が多いのも事実です。その結果、「SESで働いても将来性がない」「やっぱりやめとけ」となる声が広がりやすくなっています。
とはいえ、すべてのSES企業がブラックというわけではありません。エンジニアを大切にし、教育体制や情報共有をしっかり行っている優良企業も数多く存在するため、企業選びと事前の情報収集が非常に重要です。
7.SESに向いているエンジニアの特徴

SESで充実したキャリアを築いているエンジニアも多く存在します。特に以下のような特徴を持つ人は、SESでの働き方が合いやすい傾向にあります。
- 変化に対応する柔軟性が高い
案件ごとに使用技術や現場環境が大きく変わるため、未知の領域にも抵抗なくチャレンジできるタイプはスキルの幅を広げやすいです。 - コミュニケーションを苦にしない
クライアント先のメンバーや他社のエンジニアとの協力が欠かせないため、人間関係をスムーズに構築できる人は重宝されます。 - 自ら案件選択やキャリアプランを交渉できる
受動的に案件を与えられるだけでなく、営業担当に「この技術がやりたい」「こういう分野を伸ばしたい」と明確に伝えられる人ほど、理想に近い案件をつかめる可能性が高まります。 - 幅広い経験を積み、将来像を模索したい
特定の分野に強みを持つよりも、複数の現場を横断して自分の得意分野を探りたい人には、SESならではの多彩な案件がメリットになります。
8.優良SES企業の見極め方

SES企業は数が多いため、ブラック企業に当たらないよう注意が必要です。以下のポイントを踏まえて見極めると、ホワイトな企業を選びやすくなるでしょう。
- 還元率や経費の扱いが透明
SES単価に対するエンジニアへの還元率、交通費や資格取得費用などの負担がどうなっているかをしっかり確認します。実際の給与計算やボーナス支給の根拠が明確な企業は信頼度が高いです。 - キャリアサポート・教育体制の充実
定期的なキャリア面談や研修、勉強会など、エンジニアの成長をバックアップする仕組みがあるかどうかを見極めましょう。社内で資格取得を奨励している企業は、スキルアップに前向きな場合が多いです。 - 法令遵守・コンプライアンス意識
偽装請負や多重下請けを避けるためにどのような対策を取っているか、派遣法や労働基準法をきちんと理解しているかを面接で確認しましょう。社員の声を定期的にヒアリングする仕組みがある企業は、トラブル防止に注力している可能性が高いです。 - 配属先や案件情報を開示する姿勢
面接時に「どんな案件が多いのか」「開発と保守どちらが中心か」などを具体的に話してくれる会社は誠実です。リスク要因を隠さず説明してくれる企業なら、入社後のミスマッチが減らせます。
十分なリサーチと面接時の質問はもちろん、 ネット上の口コミサイトやSNSなども通じて 「エンジニアに還元される仕組み」や「コンプライアンス意識の高さ」 をチェックしておくことで、理想的な職場を見つけやすくなります。
9.まとめ
SESは正社員として雇用されるケースが多く、幅広い案件に携われるのが魅力ですが、配属先や還元率の不透明さなど、注意すべき点も少なくありません。実際、偽装請負や多重下請けのリスクに加え、スキルアップの方向性が見えにくいことから「やめとけ」と言われることもあります。ただし、ホワイトなSES企業も存在し、還元率の公開や教育制度の充実などを通じてエンジニアを大切にしている会社も多いです。自らのキャリア目標を明確にし、主体的に案件選択を交渉する姿勢を持ちながら、優良企業を見極めていきましょう。