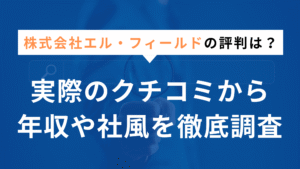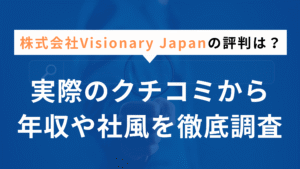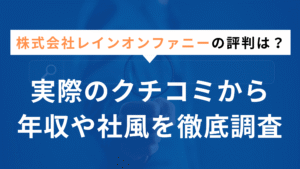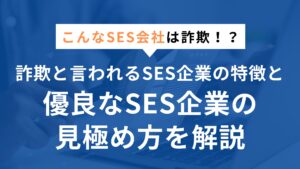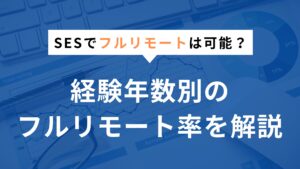SES契約の「偽装請負」とは?エンジニアが知っておくべき違法リスクと対処法
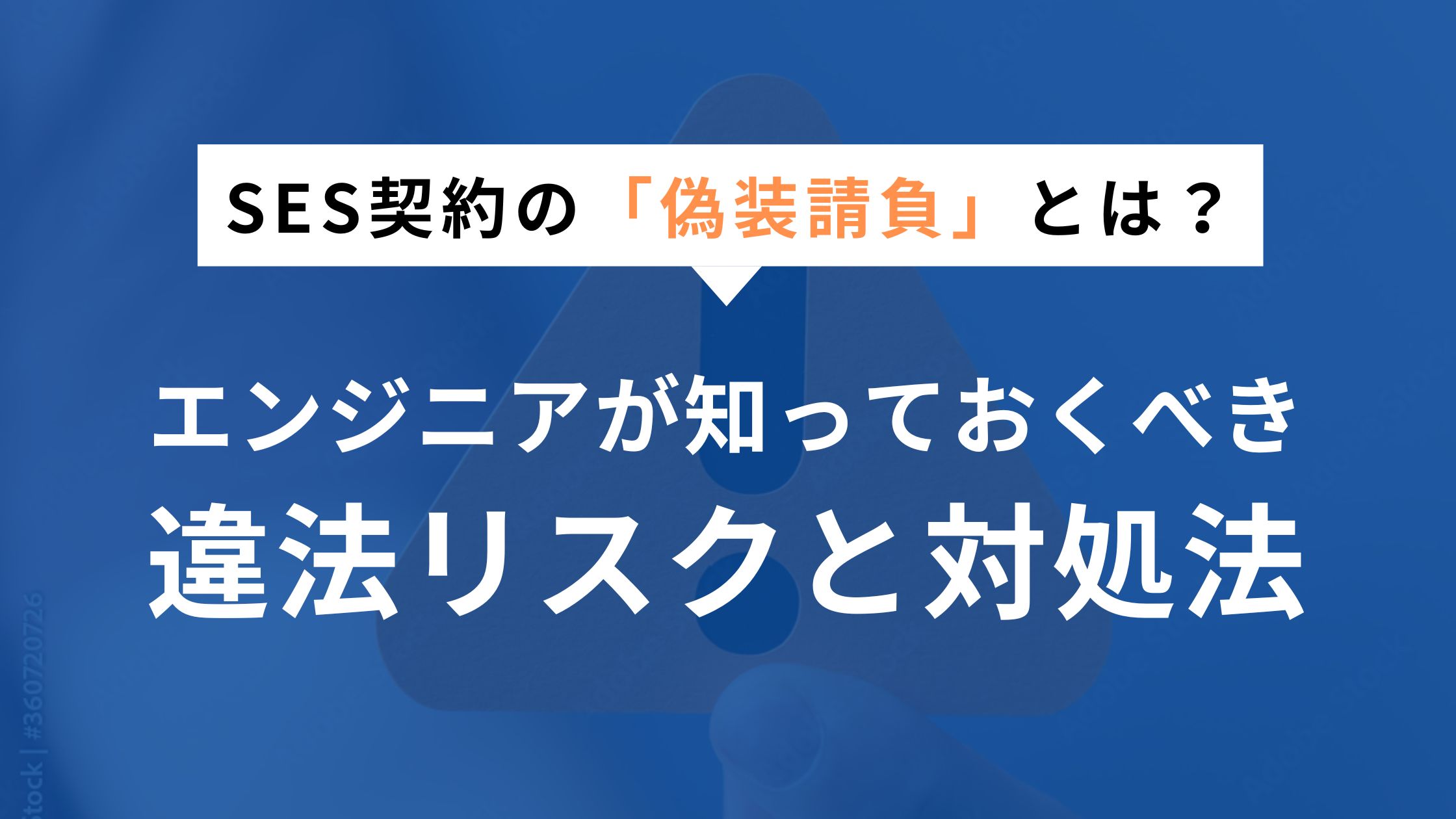
エンジニアとしてSES契約で働いていると、「偽装請負」という言葉を耳にする機会があるかもしれません。これは、実際には派遣法や契約形態の曖昧さを巡る問題をはらんだ状態ですが、具体的にどこが違法になるのか、なぜリスクが高いのかを正確に理解している人は意外と少ないでしょう。
本記事では、SES契約と偽装請負の基本事項を整理しながら、エンジニアがどのような点に注意すればよいのか、そして万が一偽装請負の疑いがある場合にどう対応すればいいかを詳しく解説します。
1. SES契約とは

SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)は、ITエンジニアをクライアント企業に常駐させ、システム開発や運用・保守などの技術的サービスを提供するビジネスモデルです。まずは、その基本的な仕組みとエンジニアとの雇用関係を確認しましょう。
1 システムエンジニアリングサービス(SES)の概要
システムエンジニアリングサービス(SES)とは、エンジニアをSES企業に所属させた上でクライアント先で業務を行ってもらう形態のことです。エンジニアは日々の業務をクライアント企業のオフィス等で実施しますが、雇用主はあくまでSES企業となります。
SESの典型的な流れ
- SES企業がクライアント企業から案件(プロジェクト)を受注する
SES企業に所属するエンジニアが、クライアント企業のオフィスで作業を行う - エンジニアの作業時間(人月)や勤務期間に応じて、クライアント企業からSES企業へ報酬が支払われる
2 SES企業とエンジニアの雇用関係
エンジニアはSES企業と雇用契約(正社員・契約社員など)を結んでおり、クライアント企業とは直接的な雇用関係を持たないのが一般的です。しかし、実際の業務ではクライアント先で働くため、指揮命令や管理主体がどこにあるのかが曖昧になりやすいという特徴があります。
- 建前上、クライアント企業とエンジニアの間には雇用関係が存在しない
- SES企業がエンジニアを管理・指揮し、クライアント企業は作業の進捗や成果を確認する立場
- 現場ではクライアント側の上司が細かい指示を出し、実質的な労務管理を行っているケースも少なくない
3 SESのメリットとデメリット
SES契約は、クライアント企業が必要な時期だけ即戦力のエンジニアを確保できる一方、エンジニア自身にとっては以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
多種多様な案件に携われるため、幅広い技術を学ぶ機会が得られる点が魅力です。未経験でも採用されやすいため、キャリアの入り口として活用できるのも大きな利点です。
デメリット
SES企業が配属先を決定するため、自分の希望とは異なる技術領域や環境にアサインされるリスクがあります。また、クライアント先の労働環境が過酷であっても、SES企業が十分に介入しないケースも存在します。さらに、偽装請負の問題に巻き込まれる可能性があり、労働法令と実態が食い違うリスクも否定できません。
このように、SESは柔軟な人材供給を可能にする一方で、エンジニアが違法な労働状態に置かれてしまうリスクが潜んでいます。次章では、そうしたリスクの背景となる「契約形態の違い」について解説します。
2. 準委任契約と請負契約の違い

SES契約が法的にどのような位置づけにあるのかを理解するためには、民法上の準委任契約と請負契約の違いを把握する必要があります。両者を混同すると、偽装請負の温床となりかねないため、ここでは基本的なポイントを整理しておきましょう。
1 準委任契約とは
準委任契約は、民法上の「委任契約」に含まれるもので、受任者(エンジニア)が一定の事務を行うことを約束し、委任者(クライアント)から報酬が支払われる仕組みです。SESの多くはこの「準委任契約」とされますが、現場での運用が適切に行われないと偽装請負の疑いが生じます。
- 成果物に対する責任を負わない
準委任では完成物の引き渡しが契約目的ではなく、「作業やサービスの提供」に対して報酬が発生します。成功・失敗にかかわらず、作業時間に対して料金が発生するという考え方です。
- 指揮命令の主体は本来SES企業にある
形式上は、エンジニアに対する細かな指示や管理はSES企業が行う想定です。しかし、現場ではクライアントが直接エンジニアに指示を出すことが多く、これが偽装請負の発端となります。
2 請負契約との違い
一方、請負契約は特定の成果物の完成を義務とする契約形態です。ソフトウェアやシステムといった完成品に対し、品質や納期に責任を持ち、納品することで報酬を得る点が大きな特徴となります。
- 成果物責任を負う
請負契約では、完成物に欠陥があった場合、請負企業が修正や保証を行わなければなりません。
- 指揮命令系統は請負企業にある
原則としてクライアントは工程の進捗や成果を確認しますが、エンジニアへの具体的な指示は請負企業が行うことになっています。
本来、SESの場合は成果物に対する責任を持たないため、準委任契約として扱われることが一般的です。しかし、現場で「ほぼ請負と同じように成果物責任を負わされる」といった矛盾が生じやすく、結果的に偽装請負へとつながるリスクがあります。
3. SES契約で注意が必要な偽装請負とは

偽装請負とは、本来は請負または準委任の契約であるにもかかわらず、実態としてクライアントが直接エンジニアを指揮・命令している状態を指します。SES形態では「準委任だから成果物に責任を負わない」としているのに、クライアント側が実質的にエンジニアを管理している現場が少なくありません。
1 偽装請負の定義
偽装請負では、エンジニアを管理すべきSES企業ではなく、クライアントがエンジニアに「これをやって」「あれを何時までに」と直接指示を出すような状況になります。また、就業管理(勤怠や休暇の承認など)までもクライアントが行っている場合が多く、これは契約形態と実態の矛盾を招きます。
2 なぜ違法なのか
偽装請負は労働者派遣法や労働基準法に抵触する可能性が高い行為です。労働者派遣法では「派遣先が直接指示を出す」場合、正規の派遣契約を結ばなければならないと定めているため、請負や準委任の名目でありながら実質的に派遣と同じ状態は違法とみなされます。
3 エンジニアへの影響
偽装請負下で働くエンジニアは、長時間残業や休日出勤をクライアントに強いられても、本来の雇用主であるSES企業がきちんとフォローしないなど、板挟みになるリスクが高まります。責任の所在も曖昧になりがちで、万一トラブルが起きた際に「どこに報告すればいいのか分からない」「自分が責任を負うのか」といった混乱が生じかねません。
自分の働きやすさに直結するため、SES企業で働くことを志す場合はこの偽装請負の問題と見分け方は必ず認識しておく必要があります。
4. こんな契約が注意!偽装請負の具体例と見分け方

偽装請負の可能性がある契約や現場には特徴があります。エンジニアとして就業先を判断する材料にしてみてください。
1 契約書上は「請負」や「準委任」でも、実態は派遣状態
クライアント先の上司がエンジニアに毎日のタスクを振り、勤怠や残業も直接管理している場合は要注意です。契約書には「請負契約」または「準委任契約」と明記されているにもかかわらず、実態としては派遣のようになっている可能性があります。
2 SES企業からの管理がほぼない
SES企業の担当営業やプロジェクトマネージャーが現場を全く訪れず、エンジニアがクライアントの上司にのみ報告している場合も危険信号です。本来、準委任であればSES企業の管理者がエンジニアをフォローするはずですが、それがなされていない状況は偽装請負になりかねません。
3 成果物に対する責任を負わされる
本来「作業やサービスの提供」による対価が準委任ですが、実際には「納品物の完成責任」をエンジニア個人が負わされるような場面がある場合、請負契約と混在していることになります。これは成果物の責任範囲があいまいになり、偽装請負の温床になりやすい典型例です。
4 見分け方のポイント
見分けるためには、指揮命令の主体がどこにあるかを確認することが重要です。さらに、就業管理や休暇取得手続き、成果物の完成責任などを誰が担っているかをチェックしましょう。クライアント先の上司に全てを任されている場合は、偽装請負を疑うべきかもしれません。
5. なぜSESで偽装請負が起こりやすいのか

偽装請負はSES以外の業態でも起こり得ますが、IT業界におけるSES契約では特に頻繁に指摘される問題です。その背景には、派遣法との兼ね合いやITプロジェクトの複雑性が関係しています。
1 派遣法との兼ね合い
派遣法には、派遣期間の上限や特定派遣の廃止、派遣先責任の明確化など、さまざまな規制が盛り込まれています。これを回避するために「SES(準委任)だから派遣ではない」と名目を変更する企業があり、実態は派遣同然であるにもかかわらず、契約だけは準委任としているケースが後を絶ちません。
2 ITプロジェクトの複雑性
ITプロジェクトでは仕様変更や緊急対応が頻繁に発生するため、クライアントがエンジニアに直接指示を出したほうが早いと判断しがちです。SES企業の管理者を経由して指示を出すには時間がかかるため、現場の要望が「とりあえずエンジニア本人に言えば済む」という方向へ流れてしまうのです。
3 人手不足の現場事情
IT業界全体に深刻な人材不足が続いており、クライアント企業は「とにかくすぐにエンジニアを投入してほしい」というニーズを持っています。SES企業も契約を成立させるために、形式的には準委任としつつ、実際にはクライアントが指示命令を出す派遣的な働かせ方を黙認してしまう場合があります。
6. 偽装請負にならないための注意点

偽装請負を回避するには、エンジニア自身が契約内容をきちんと把握し、必要に応じて適切な対策を取ることが大切です。同時に、SES企業側にもコンプライアンス意識を高め、正しい労働環境を作る責任があります。
1 エンジニア側の対策
エンジニアにできる対策としては、まず自分がどのような契約形態で働いているかを正確に把握することが挙げられます。
- 契約内容を事前に確認する
準委任なのか、請負なのか、それとも派遣契約なのかを書面で確かめておきましょう。SES企業の説明を鵜呑みにせず、自分で理解する姿勢が大切です。
- 面談時に指示系統を確かめる
クライアント先での業務指示は誰が行うのか、SES企業のプロジェクトマネージャーや営業担当はどの程度関与してくれるのかを質問して、曖昧な回答があれば注意が必要です。
2 SES企業側の対策
SES企業としても、契約形態に合った適切な運用をすることで、偽装請負を防ぐ責任があります。例えば下記のような対策がSES企業側では考えられます。
エンジニアの皆さんが直接関わる領域ではありませんが、こう言った対策を行っている企業は偽装請負のリスクに対して誠実といえるため、優良な企業であると言えます。積極的にチェックしましょう。
- 契約書の正確な作成
準委任なら準委任、請負なら請負、派遣なら派遣と形態を明確に示し、指揮命令系統を契約書で定めることが重要です。
- クライアントへの事前説明
「この契約は準委任ですので、エンジニアへの直接的な細かい指示は控えてください」と周知徹底する必要があります。どうしても指示が必要な場合は派遣契約を検討するなど、合法的な手段をとるべきです。
- エンジニアとの定期面談
実際の現場で偽装請負状態になっていないかをモニタリングし、問題があればクライアントと交渉するなど迅速に対応します。
- 社内教育とコンプライアンス強化
偽装請負や経歴詐称などの危険性を社内に周知し、リスクを未然に防ぐ仕組みづくりを行うことが大切です。
まとめ

SES契約では「準委任」として作業提供に対する報酬を受け取る形態を取っているにもかかわらず、実態がクライアントによる直接指揮命令となっている場合、偽装請負とみなされるリスクが高まります。これは労働者派遣法や労働基準法に違反する可能性があり、エンジニア本人も法的リスクや過酷な労働環境に巻き込まれる恐れがある点に十分注意しなければなりません。
契約内容を確認し、指揮命令系統が正しく整備されているかを見極めることは、エンジニアの身を守るうえでも非常に重要です。もし現場の実態が疑わしいと思ったら、SES企業に相談したり、法的機関へ問い合わせたりして、違法状態から脱却できるよう行動を起こしましょう。SES企業側も、透明な契約書の作成やクライアントとの連携によって、エンジニアにとって適正な労働環境を整える努力が欠かせません。