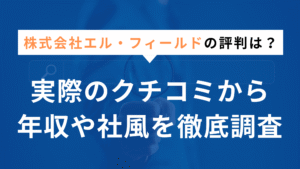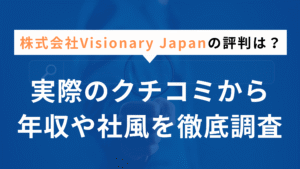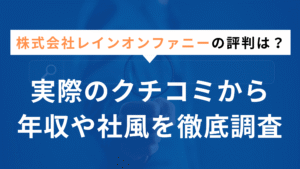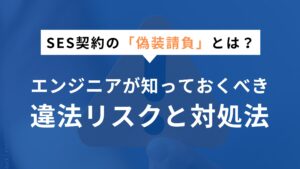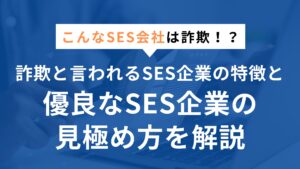SESでフルリモートは可能?経験年数別のフルリモート率を解説
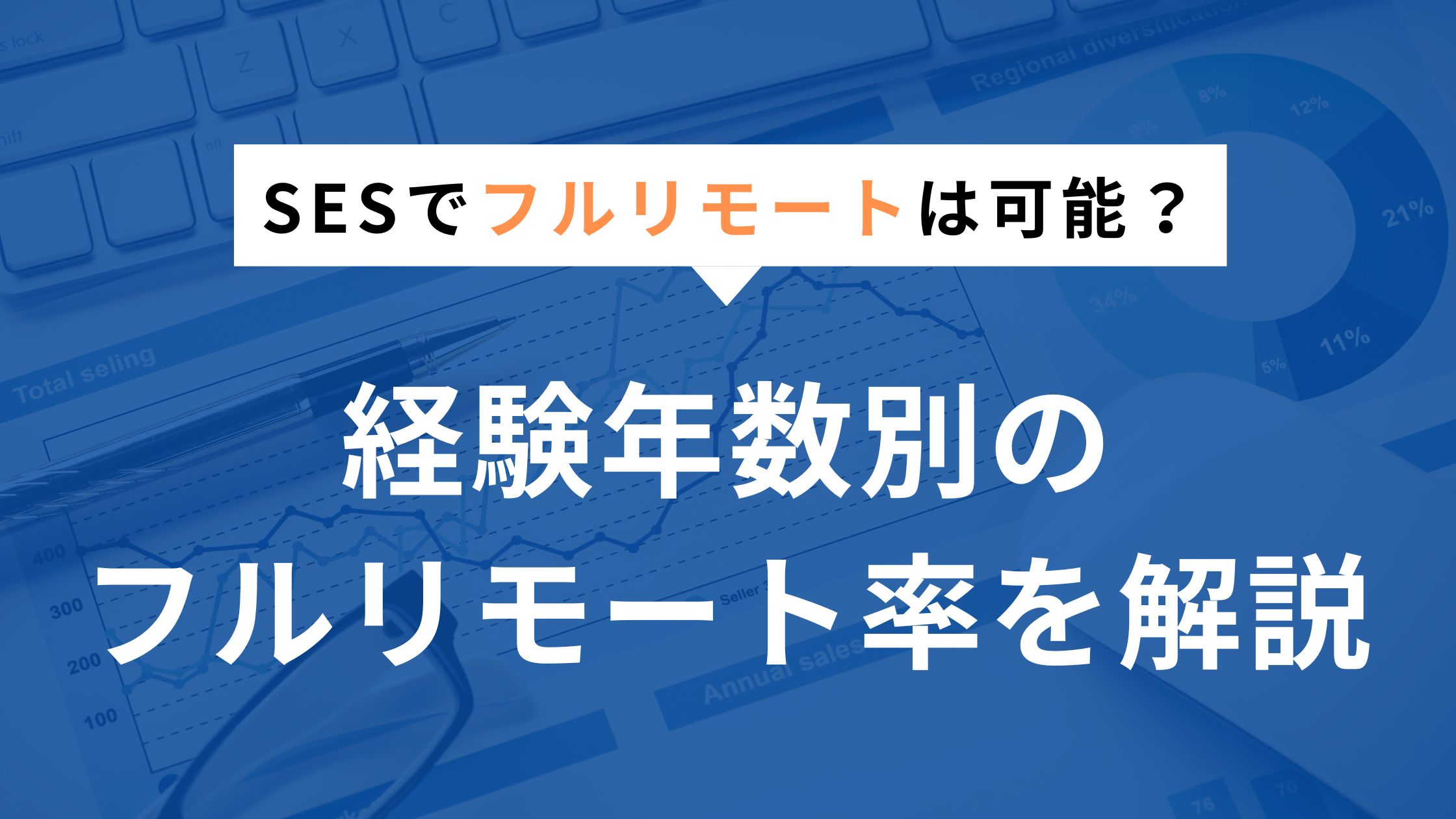
近年、リモートワークがIT業界において一般的になりつつありますが、SES契約のエンジニアにとっては依然としてハードルが高いと感じる方も多いでしょう。そこで本記事では、SESでのフルリモート事情を深掘りしながら、経験年数によるフルリモート率の違いや、その働き方のメリット・デメリット、さらにフルリモートに適した人の特徴を徹底解説します。
1. SESでフルリモートワークのトレンド

SES契約でフルリモートが広がる背景には、感染症拡大による緊急対応が大きく影響しました。しかし、その後の情勢変化によって実情は徐々に変わりつつあります。まずは、コロナ禍を経てどのようなトレンドが生まれているのかを整理してみましょう。
1 コロナ感染拡大で一時期は増加傾向に
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界的に拡大した2020~2021年頃、IT業界全体が急速にリモートワークへ切り替えました。緊急事態宣言や出社制限が出されるなか、クライアント企業は「オフィスに人を集めない」方針を打ち出し、SESエンジニアを含め在宅勤務を認めるケースが急増したのです。
具体例
これまで「情報セキュリティ上リモートが難しい」とされていた企業が、短期間でVPN環境を整え、SESエンジニアにも在宅勤務を適用。
SES企業も貸与PCやセキュリティルールを整え、オンラインで進捗を管理する必要に迫られました。
こうした緊急対応によって、「SESでのフルリモートは不可能ではない」という認識が一気に広がったのは事実です。長期間にわたってフルリモートが続いた案件も珍しくなく、実務上の問題が意外に少ないと感じた企業も多かったようです。
2 現在はオフィス回帰がトレンド
一方、2022年以降コロナ禍が落ち着くにつれ、「オフィス勤務の意義を再確認したい」という声が増え、出社を基本に戻そうとする企業が目立ち始めました。
その背景には 大手IT企業やSIerなどを中心に、「対面コミュニケーションや社内カルチャーの醸成が大切」という考え方が復活したことが挙げられます。
クライアントがオフィス勤務を必須化すれば、SESエンジニアもそれに従わざるを得ないためフルリモート案件は減少方向となっています。
ただし、一部のWeb系企業やスタートアップでは、依然としてフルリモート体制を維持している場合もあります。コロナ禍でフルリモートを実施した経験から「問題なく業務が進められる」と判断した企業は、そのまま在宅勤務を継続するケースもあるのです。
2. SESのフルリモートのメリット・デメリット

フルリモート勤務が可能なSES案件では、通勤不要などエンジニアにとって魅力的なポイントが多い反面、リモート特有の課題も存在します。ここでは、フルリモートの利点と弱点を押さえておきましょう。
1 メリット
フルリモート勤務がもたらす最大の恩恵は、やはり通勤時間の削減ですが、それ以外にも作業集中しやすいなどのメリットがあります。
- 通勤時間がなく自由時間が増える
都市部での長時間通勤から解放されるのは、大きなストレス軽減につながります。往復の移動が不要になることで、家事や睡眠、自己学習などに時間を充てられるのが魅力です。
- 周りに人がいないので集中しやすい
クライアント先やオフィスの雑音や雑談がない分、自宅であれば作業に没頭しやすいと感じる人も少なくありません。ただし、十分に在宅環境が整っていない場合や同居家族やペットがいる場合は逆に集中できない要因になるため、環境の整備がカギとなります。
2 デメリット
反面、フルリモートならではの課題も無視できません。コミュニケーションの難しさやプライベートとの境界の曖昧化など、人によっては大きな負担となる可能性があります。
- コミュニケーション不足、孤独感
オンラインのみのやり取りでは雑談や情報共有がしづらく、SESの場合はチームメンバーが全員別企業所属ということも珍しくありません。孤独を感じやすく、問題が起きても相談が遅れるケースがあるため、メンタル面のケアも重要になります。
- 仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすい
自宅が仕事場になることで、つい深夜まで作業を続けてしまったり、常にチャットやメールの通知を気にしてしまったりと、オンとオフの切り替えが難しくなることがあります。自己管理能力や環境づくりが不可欠です。
3. SESのフルリモートワークに向いている人の特徴

フルリモートはすべてのエンジニアにとって理想の働き方ではありません。向き不向きがあるため、ここではフルリモートに適した人の特徴を挙げてみます。
1 自己管理能力が高い
リモート下では、上司や同僚がそばにいないぶん、仕事の進捗を自分で管理することになります。タスク管理やスケジュールの調整が苦手な人は、サボり過ぎたり、逆に働き過ぎたりしがちです。タイムマネジメントツールなどを使いこなし、自律的に動ける力が求められます。
2 テキストベースのコミュニケーション能力が高い
チャットやメールといった文章でのやり取りが増えるため、言葉の選び方やニュアンスの伝え方が重要になります。オンライン会議でも、画面共有やホワイトボード機能などを活用し、相手に分かりやすく伝えるスキルが必要です。
3 デメリットを補うほどのスキルや経験がある
特にSES契約では、コミュニケーションロスやトラブル時の対応がオフィスより煩雑になる可能性があります。未経験や駆け出しのエンジニアの場合こういった背景でフルリモートは難易度が上がりますが、一定の実務経験や自己解決力があるエンジニアにとっては大きなデメリットとならずスムーズに業務が進行できる可能性が高いです。
4. 経験年数別のフルリモート率

ここでは、実務経験年数とフルリモート案件に参画できる可能性の目安を紹介します。あくまで一般的な傾向であり、実際の働き方は企業文化やプロジェクトの特性によって左右される点をご留意ください。
1 実務経験3年未満は約20%
キャリア初期のエンジニアは、技術力よりも「学習姿勢」や「吸収力」が重視されるフェーズです。そのため、先輩社員やメンターからの直接指導が前提となり、フルリモートでの勤務はややハードルが高くなります。
傾向としては以下の通りです:
- フルリモート勤務は限定的で、出社前提または週1~2回の出社が求められるケースが多い
- プロジェクトによっては、最初の数ヶ月は常駐、その後リモート切り替えというステップを踏むこともある
- 一部のスタートアップやフルリモート推奨企業では、未経験でも在宅勤務を認める場合があるが、例外的な事例にとどまる
このような背景から、3年未満のエンジニアがフルリモートで働くには「クライアント企業の柔軟さ」と「自身の学習スピード」が鍵となります。
4.2 3~5年で約50%
中堅層と呼ばれるこの時期は、ある程度の技術スタックに習熟し、自立してタスクを進められる力が求められます。そのため、フルリモートでの働き方が徐々に現実的な選択肢になってきます。
この段階の特徴は以下の通りです:
- 設計〜実装まで一人称で対応できるため、物理的にチームと同じ空間にいなくても支障が少ない
- WebサービスやSaaSなど、クラウドを活用したプロジェクトではリモート前提での稼働が一般的
- 通信環境やタイムマネジメントを自己管理できることが前提条件となるケースも
一方で、例えば下記のケースではフルリモートができないケースもあります。
- 一部技術領域の知見が浅く、チームメンバーの手を借りる必要がある(同じ空間で同期的に連携する必要がある)。
- 外部への持ち出しが禁じられている個人情報を取り扱う
このように、まだフルリモートができないケースも当然あるものの、「週5日フルリモート+フレックス制度」など、自由度の高い働き方を選べる可能性が一気に高まります。
3 5年以上は80%
ベテラン層のエンジニアにとっては、フルリモート勤務はもはや「選べる働き方」の一つとして定着しつつあります。特にリーダー職やアーキテクトとしての役割がある場合は、フルリモートでも十分にプロジェクト推進が可能と判断されます。
このレベルに達すると以下のような状況が増えてきます:
- 設計レビューや進捗管理など、非対面でも実行できる上流工程に関わる機会が増加
- チーム全体の生産性を意識した「リモートリーダー」としての役割を任される
- リモートに最適化された組織(Slack・Notion・Zoomなどの活用)で、フルリモート前提のプロジェクトに参画
一方で、例えば下記のケースではフルリモートができないケースもあります。
- 外部への持ち出しが禁じられている個人情報を取り扱う
- メンバー教育がメインの案件のため、対面での指導が必要
このように、全ての案件でリモートが可能というわけではありませんが、5年以上の実績があれば「出社ありきのプロジェクト」は避けやすく、自分に合った働き方を選べる自由度が格段に広がります。
5. まとめ

フルリモートが一気に普及したコロナ禍も一段落し、オフィス回帰の動きが再燃しているIT業界ですが、フルリモートを望むエンジニアのニーズは依然として根強いのが現状です。ただし、SES契約においてはクライアント企業側の意向が大きく左右するため、とりわけ未経験や経験の浅いエンジニアにとってはリモート案件に参画するハードルが高い点を理解しておく必要があります。
最終的にはプロジェクトの性質や企業方針にも依存するため、絶対ではありません。しかし、自己管理能力やコミュニケーション力、さらに専門スキルを高めていけば、フルリモートを選択しやすくなるのは確かです。もしフルリモートを強く希望するなら、早い段階から在宅ワークに向けたスキルアップと経験の積み上げを意識し、案件選択の幅を広げておくと良いでしょう。