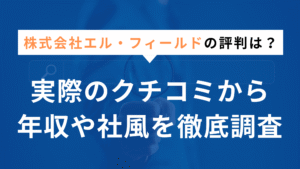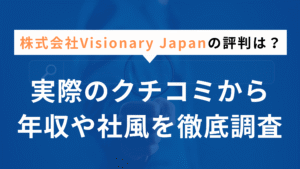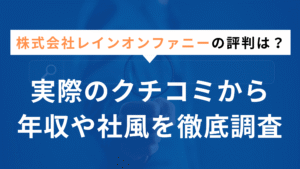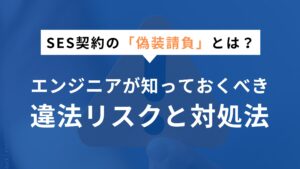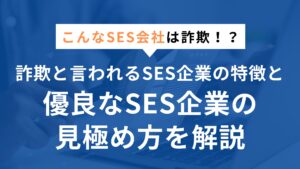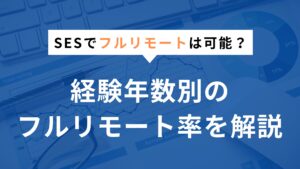【SES企業の転職】転職の最適なタイミングや転職先の選び方を徹底解説
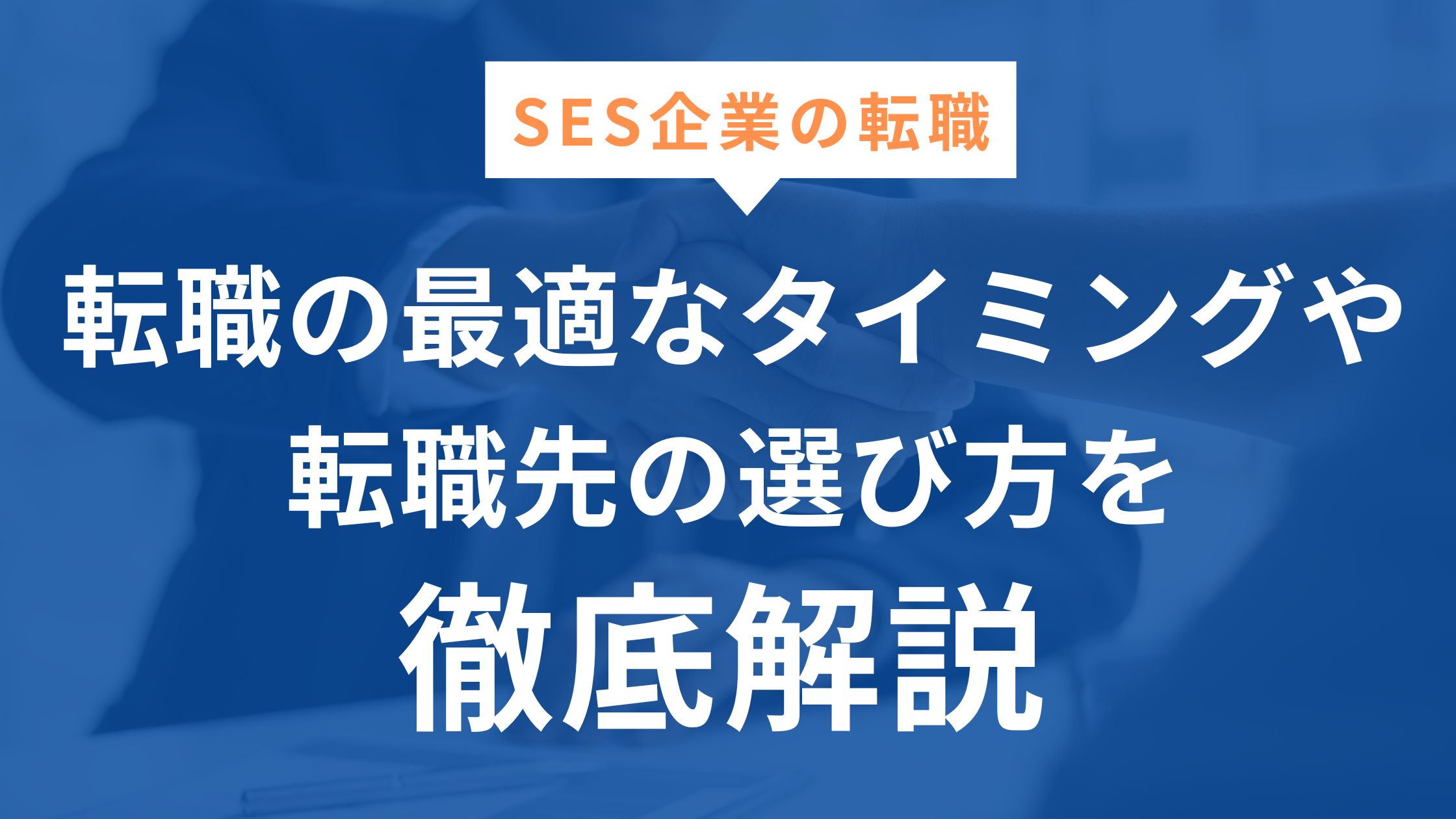
SESで働いていると、「キャリアアップや転職は難しい」という声を耳にすることがあるかもしれません。しかし、実際には幅広いキャリアパスへの転職が十分可能です。本記事では、転職の最適なタイミングやおすすめの転職先、成功のコツを詳しく解説します。
現場経験の活かし方や面接時のアピールポイントなど、読めば今日から実践できる情報を網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。
SES企業から他のIT企業へ転職できないって本当?

「SESは転職が難しい」と言われることがありますが、果たしてそれは事実なのでしょうか。結論から言えば、SES出身でも転職は十分に可能です。実際にSESから大手自社開発企業や外資系IT企業へキャリアチェンジをした人は数多く存在します。
しかし、なぜ「転職しづらい」という声が根強くあるのか、その背景を理解しておくことは大切です。世の中には、SESと聞くと「エンジニアとしての成長が難しい」「SES出身者はスキルがまちまち」と偏見を持つ方も一部いらっしゃいます。そうしたイメージを払拭するためには、自分のキャリアを客観的に見直し、「何ができるのか」「何を目指しているのか」を明確に示せるよう準備する必要があります。
本記事を通じて、SESエンジニアが転職において抱えがちな不安や疑問を解消し、自分に合った最適な転職先を見つけるためのヒントを得ていただければ幸いです。単なる情報収集だけでなく、「いまの会社に残るべきか、辞めるべきか」「本当にやりたい仕事は何なのか」というキャリアの根幹を改めて考え直すきっかけにもなるでしょう。
SESは転職できないと言われる理由

SESに限らず、「〇〇出身だと転職が厳しい」といった声はIT業界でよく耳にします。実際、なぜ「SESは転職できない」「SES出身者は不利」と言われがちなのでしょうか。ここでは代表的な理由をいくつか挙げます。
1. スキルの方向性が定まらないケースが多い
SESの現場では、顧客企業の要望に合わせて業務を行うため、幅広い技術や案件を経験する可能性があります。これは一見するとメリットとも言えますが、ただ漫然とさまざまな案件を転々としていると、専門性が育ちにくいというデメリットが生じやすいです。例えば、あるプロジェクトではテスト工程ばかり担当し、次のプロジェクトでは運用・保守のみ、その次では別の言語の開発……などとスキルが断片的に積み上がってしまい、「どの技術をどのくらい深く扱えるのか」という点でアピールが難しくなります。
2. 転職でアピールできる成果物が示しづらい
クライアント先の契約形態やプロジェクト内容によっては、具体的な開発事例や成果物を外部に公開できない場合があります。自社開発や受託開発と違い、ポートフォリオを示す機会が限られるため、転職面接では実績を言葉でしか伝えられないことも多いです。
面接官からすると、「さまざまな案件に携わってきたようだけれど、具体的にどんなシステムを、どの規模で開発し、どれほどの成果を上げたのか」が把握しづらく、評価に悩むケースがあります。
3. 自社開発や受託企業との文化や評価基準の違い
自社開発や受託開発の現場では、プロダクトやサービスをゼロから考え、運営し、ユーザーの声を取り入れながら改善していくという文化が根強いです。技術選定や上流工程の経験も重視されやすく、ビジネス的な視点を伴ったエンジニアが求められます。
一方、SESでは人月契約が中心となり、「与えられた役割を期限内にこなす」ことが最優先となりがちです。その結果、どうしても技術選定や要件定義といった上流工程に携われる機会が少なくなる場合があり、「SES出身者=上流経験が乏しい」と見られる可能性があります。
SESでも転職できる人・できない人の特徴

「SESは転職しづらい」というイメージはあるものの、実際には問題なく転職している人も大勢います。その差はどこにあるのでしょうか。ここでは、転職を成功させやすい人の特徴と、逆になかなか転職に踏み切れない・内定を得られにくい人の特徴について解説します。
転職できる人の特徴
1. スキルセットや目標が明確
「JavaでWebアプリ開発を極めたい」「インフラ構築のスペシャリストになりたい」など、具体的なキャリアの方向性があると、案件選定や学習の方向がブレないため、実務経験を着実に積み重ねやすいです。
面接でも「自分は何を得意としており、どの領域に興味があるのか」を一貫したストーリーで示すことができれば、企業側から高く評価されるでしょう。
2. 現場での成果を可能な限り“見える化”している
SES案件では、守秘義務の都合で詳細を公開できない場合もありますが、「プロジェクトを円滑に進めるためにどんな工夫をしたか」「新ツールの導入を提案して効率化を図った」などの実績を定量的・定性的に記録しておくと、大きなアピール材料になります。
「単にテストをこなした」ではなく、「テスト工数を20%削減する仕組みを提案し、採用された」など、具体的な数字や方法を挙げられると説得力が高まります。
3. 自己学習や情報収集に積極的
与えられた案件だけでなく、プライベートでの勉強やOSSへのコントリビュート、技術ブログの執筆など、多角的にスキルアップを図っているエンジニアは転職市場でも評価されやすいです。
会社での経験にプラスアルファのアウトプットがあると、「学習意欲が高く、主体的に行動できる人材」として見てもらえる可能性が高まります。
4. 交渉力・コミュニケーション力がある
SESでは、営業担当やクライアントとの折衝が不可欠であり、そこで培われるコミュニケーション力は転職先でもプラスに働くことがあります。
また、自分の希望案件やキャリアプランを社内で交渉し、自身の意思を通してきた経験があれば、それは「主体的にキャリアを築こうとする姿勢」として非常に高く評価されるでしょう。特にマネジメント志向やリーダー志向のあるエンジニアは重宝されがちです。
転職できない人の特徴
1. やりたいことが曖昧なまま案件を転々とする
エンジニアとしての方向性が定まらず、何となく目の前に来た案件を受け続けるだけでは、数年後に振り返った時に「スキルが断片的」「深みがない」という状態に陥りがちです。
面接で「なぜその技術を使ってきたのか」「これからどんなキャリアを築きたいのか」を問われても答えられず、印象が弱くなってしまいます。
2. 実績を形に残していない
プロジェクトでの貢献内容や成果を記録しておらず、担当範囲すら曖昧な場合は、転職活動でアピールできるポイントが皆無になってしまいます。
「ただ在籍していただけ」「運用・保守をやっていたらしいが詳細不明」という印象になってしまうと、企業も採用を決断しづらいでしょう。
前述の通り、具体的な開発事例や成果物が公開できない場合であっても、実績を定量的・定性的に記録しておくことでスムーズにアピールができるはずです。
3. 会社任せ、環境任せ
営業担当やクライアントに不満があっても「仕方がない」と受け身になり、自分からは何も行動しないタイプの人は、案件や給与の向上、スキルアップの機会を逃しがちです。
受け身のまま転職活動を始めても、求人の比較や面接準備、自己分析などをおろそかにしてしまいがちで、不合格になりやすいパターンがあります。
SES転職の最適なタイミング

転職に成功するかどうかは、「どのタイミングで行動を起こすか」も大きく影響します。SESエンジニアとして働く中で、いつ転職を検討すべきか、代表的なタイミングを押さえておきましょう。
1. 案件が一区切りついた時期
SESエンジニアの場合、プロジェクト完了や区切りの良いタイミングは転職を検討しやすい時期です。新しい案件に入る前なら、次のキャリアにスムーズに移行しやすくなります。
また、案件終了の時期は「どの技術をどの程度身につけたか」を振り返りやすく、職務経歴書を整理する絶好の機会でもあります。
2. 経験年数が2~3年を超えた頃
一般論として、「SESでも最低2~3年は続けて実務経験を積むと転職市場でアピールしやすい」と言われることがあります。あまりに早い段階での転職は、「忍耐力がない」「スキルが浅い」と見られるリスクがあります。しかし、一方で5年以上ずっと同じような案件にしか関わっていないと、企業から「同じ環境でしか通用しないのでは?」と疑問を持たれる場合もあります。2~3年をめどにキャリアの方向を見直すのは、ひとつの定石と言えるでしょう。
3. スキルアップの限界を感じた時
SESで働いていると、「テストや運用ばかりで開発経験を積めない」「ずっと古い技術しか触れない」など、スキルアップが頭打ちになるケースがあります。
同じ環境にいる限り成長が見込めないなら、思い切って転職を検討するのも一手です。IT業界の技術トレンドは移り変わりが激しいため、環境を変えて新しい技術や領域にチャレンジする方がキャリアアップにつながる可能性も高くなります。
4. 案件待機期間中
SESの世界では、案件が切れて次のプロジェクトが見つかるまで待機させられる「案件待機期間」があります。会社によっては待機中の給与が不透明だったり、学習機会が確保されていなかったりと、不安が募りやすい時期でもあります。逆に言えば、転職活動に時間を割きやすいタイミングとも言えるので、この期間を無駄にせず、応募企業のリサーチや職務経歴書のブラッシュアップ、面接対策などに活用するのがおすすめです。
SESから選ぶべき転職先

「SESからの転職先にはどのような選択肢があるのか?」と迷う方も多いかもしれません。ここでは、代表的な転職先の種類をいくつか挙げ、そのメリット・デメリットを解説します。
1. 自社開発企業(事業会社)
メリット
- 自社プロダクトを長期的に育てられるため、サービス全体の改善や機能追加に深く携われる
- 技術選定やサービス運営にも関わりやすく、エンジニアとしての幅が広がりやすい
- ユーザーフィードバックを直に得られるため、ものづくりのやりがいを強く感じられる
デメリット
- 非常に人気が高く、採用倍率が高め
- 技術力だけでなく、サービスへの興味やビジネス視点などを求められるケースが多い
- 一度プロダクトが完成したら運用保守業務が多くなり、技術力の更新がしづらい
2. 受託開発企業(SIer、Web制作会社など)
メリット
- 請負契約がメインで、自社チーム主体で案件を管理しやすい
- 顧客企業ごとに異なるプロジェクトに携わり、幅広い経験を積める
- 技術選定や仕様策定などに一定の自由度があるケースもある
デメリット
- 納期や予算に追われ、残業やタイトなスケジュールになる可能性がある
- エンドユーザーとの距離があり、「自社開発のようなダイレクトな反応を得にくい」と感じることもある
- 色々な開発言語での受託をする事が多く、どの言語も中途半端にしか理解できない
3. 現職とは異なるSES企業
メリット
- SESの働き方に抵抗がない場合、より好条件や案件選択の自由度が高い企業への転職で待遇改善が見込める
- 単価や契約内容を透明化している優良企業を選べば、いまより高い年収を得られたり、スキルアップを支援してもらえる可能性がある
デメリット
- 結局「人月」で売られる仕組みは変わらないため、担当者や案件の質にばらつきがある
- 強い専門性を磨くための環境が整っていない企業に入ると、また同じ悩みを繰り返す可能性がある
4. フリーランス
メリット
- 高単価案件に参画できる可能性があり、収入面で大きく伸ばせる
- 案件選択の自由度が高く、ワークライフバランスを自分でコントロールしやすい
デメリット
- 営業や経理などをすべて自分で管理する必要がある
- 社会保険や福利厚生が手薄で、仕事が途切れるリスクに対する備えが必須
- 年齢を重ねると案件がなかなか獲得できない
- 出来る仕事しか任されない為、成長出来る機会が少ない
- 信用がない場合が多く、PM案件がほぼない
SESからの転職を成功させる方法

ここでは、実際に転職活動を進める際に押さえておくべきポイントを具体的に紹介します。転職の成功は、事前の準備と計画が鍵を握ります。
1. 自己分析とキャリアの棚卸し
まずは、「自分が何を得意としており、どの領域で将来活躍したいのか」をはっきり言葉にできるレベルに落とし込みましょう。
職務経歴書を作成する際には、
- どんな案件で何を担当し、どんな成果を上げたか
- プロジェクト全体の体制や、開発規模、使用した言語やフレームワーク
- チームでの役割や工夫したポイント、改善提案の例
などを箇条書きにして整理すると、面接でも説得力が高まります。
2. 転職エージェントや転職サイトを活用
SES出身エンジニア向けに特化した転職エージェントや、IT業界専門のエージェントを活用することで、最新の求人動向や非公開求人を紹介してもらえる可能性が高まります。
面談の際は、「自社開発企業で上流工程をやりたい」「受託開発で幅広い案件に携わりたい」など、具体的な要望をはっきり伝えましょう。
また、転職サイト(リクナビNEXT、doda、Green、Wantedlyなど)を併用することで、企業の口コミや募集要項をより網羅的に確認できるため、必ずチェックしておきましょう。
3. スキル証明のためのアウトプット
SES案件は守秘義務の兼ね合いで実績を開示しづらい一面がありますが、プライベートの活動で補完する方法があります。
- GitHubでのコード公開
- 技術ブログやQiitaでの発信
- OSSプロジェクトへのコントリビュート
- 資格取得(AWS認定資格、基本情報技術者、応用情報技術者など)
これらはスキルレベルを客観的に示す手段として非常に有効です。応募先企業の面接官も、「この人は日頃から学習意欲を持っているか」を重視しているため、積極的にアピールしましょう。
4. エンジニア同士のつながりの強化
SNSや勉強会、ITエンジニア向けのコミュニティに参加することで、思わぬところから良い求人情報が得られる場合があります。
特に、エンジニアコミュニティはオンラインでも交流しやすく、イベントや懇親会を通じて企業の技術担当者と繋がるチャンスも豊富です。知人や先輩エンジニアから直接「うちの会社を紹介するよ」と誘われることもあるため、ぜひ情報を広く集めてみましょう。
5. 面接対策:SESの経験をどうアピールするか
転職面接では、SES特有の経歴をネガティブに捉えられないようにすることがポイントです。たとえば、「短期的に多くのプロジェクトを経験し、多角的な視点で問題解決に取り組んできた」担当範囲は限定的だったかもしれないが、その中で生産性を上げる取り組みをしてきた」「チームやクライアントとのコミュニケーションを円滑にする施策を実践した」など、ポジティブな切りや工程を深く掘り下げる姿勢を見せることで好印象につながります。
優良SES企業の見極め方

転職活動をする前に、現在所属するSES企業が本当に自分に合わないのかを見極めるためにも、またはSESからSESへの転職を検討する際にも、優良SES企業を選ぶ基準を押さえておきましょう。
1. 還元率や単価の公開度
エンジニアに支払われる報酬の元となる契約単価がどのように設定・公開されているかは、企業の誠実さを測る一つの指標です。社内で「還元率80%以上!」とうたっていても、実質的には経費を引かれていて手取りが低い…といったケースもあるため、面接時や社員口コミサイトなどを通じてしっかり確認しましょう。
2. キャリアアップ支援と教育制度
研修や勉強会、資格取得支援など、エンジニアのスキルアップに投資している企業は人材を大切にしている傾向があります。
案件アサインの際に希望をどれだけ聞いてくれるのか、定期的な1on1面談があるのか、自己啓発支援制度はあるのかなどをチェックし、エンジニアとしてキャリアアップしていける環境なのかどうかを見極めましょう。
3. コンプライアンス意識
SES業界で問題となってきた偽装請負や、多重下請け構造などに対して、会社としてどのように対策を取っているかは重要な判断材料です。
- 派遣法を遵守しているか
- 労務管理が徹底されているか
- 契約や法令に関する説明が社内でオープンにされているか
などを確認し、社員を守る体制が整っている企業を選ぶことが大切です。
4. 配属先のバリエーションと案件の質
優良SES企業は、多種多様な開発案件を確保しやすい営業基盤を持っています。常に最新技術を用いる案件や、長期的にスキルアップできるプロジェクトに参画できるかどうかは、キャリア形成に大きく関わります。
「運用・保守やテストばかりに偏っていないか」「最新のクラウド技術やアプリ開発案件はあるか」など、面接時に具体的に質問してみるといいでしょう。
まとめ
SES出身エンジニアが「転職しづらい」と言われるのは、スキルの方向性が定まりにくかったり、成果物を公開しづらかったりといった構造上の理由からくるイメージも大きいです。しかし、実際にはSESからでも事業会社や外資系IT企業などへの転職を成功させている人は数多くいます。
転職を成功させる鍵は、自分がどんなエンジニアとして成長したいのかを明確にし、実績や成果を“見える化”してアピールできるように準備することです。職務経歴書や面接で具体的な数字や工夫点を示すことで、SESならではの経歴をポジティブに捉えてもらうことができます。
また、転職先としては自社開発(事業会社)・受託開発・別のSES企業・フリーランスなど選択肢が豊富に存在します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分のキャリアプランやライフスタイル、価値観に合った働き方を選ぶのが大切です。「SESだから転職は難しい」と思い込まず、積極的に情報収集や人脈づくり、アウトプット活動を行い、魅力的なキャリアを実現できるよう行動してみてください。